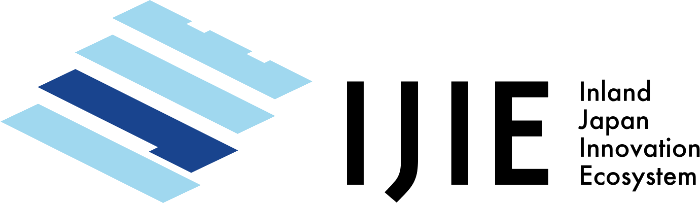小児心不全で亡くなる乳幼児を一人でも減らしたい
~βアレスチンバイアスアゴニストの有効性を検証し、乳幼児の心不全による死亡率減少、安全な移植待機時間の延長、QOL向上を目指します~

本研究会の活動のご紹介
本研究会では、これまでに全くなかった新しい種類の小児心不全治療薬の開発を目指しています。
赤ちゃんは、お母さんのお腹の中では胎盤から酸素をもらっていますが、誕生後は自分で呼吸して酸素を取り込まなければなりません。そのため誕生時に血流が大きく変化しますが、この変化に体が完全に適応するまでのしばらくの間、心臓には大きな負担がかかります。ですので、心臓に何らかの異常を持って生まれた赤ちゃんの約60%は、1歳までに心不全を発症します。心不全を発症した赤ちゃんは、授乳中に強く汗をかいたり、成長不良になったりし、亡くなる可能性が高まります。
手術などで治療できる心臓病も少なくありませんが、それが不可能で心不全になった場合、心臓移植しか治療法がない場合もあります。しかし年齢が若いほどドナーの不足は深刻で、長い移植待機期間が必要となります。このとき人工心臓が有効ですが、人工心臓も大変不足しています。ですので、良い小児心不全治療薬が是非とも必要です。
しかし残念ながら、このような治療薬は現在ほとんどありません。そのため、仕方なく成人向けの心不全治療薬の適用外使用で治療がなされていますが、これには色々な問題があります。
- まずは、ほとんどの成人用治療薬が、小児でも有効で安全か科学的に証明されていないことです。
- また適用外使用の場合、保険診療の対象とならず、家族に高額な医療費負担が生じる可能性があります。
- さらにもし副作用が生じても、適用外使用では医薬品副作用被害救済制度の対象とならず、医療費、年金等の給付を受けられない可能性があります。
これほど医学が発達した現在でも、小児心不全治療薬が開発されていないのには多くの理由がありますが、本研究会ではアカデミアとして小児の心臓の特性の科学的研究を行い、それを通して、
- ボトムアップ式に理想の小児心不全治療薬を提唱し、その有効性と安全性を証明し臨床応用を図る
- 小児科医師、患者家族、産官学に働きかけ、小児心不全治療薬の開発が進展するような環境を醸成してゆく
という、2つのことを目指しています。
(本研究会の活動の内、臨床検体の解析は日本小児循環器学会 小児心不全治療薬開発研究委員会*、動物モデルを用いた解析は科研費、蛋白質結晶の解析はJAXA、BINDS、インタープロテイン社、SpaceBD社の支援を受けています。)
研究責任者/信州大学医学部発達薬理学研究グループ 特任教授 山田 充彦
*【日本小児循環器学会 小児心不全治療薬開発研究委員会メンバー】
新しい小児心不全治療薬のコンセプト

赤ちゃんの体内では、誕生後の血流変化に耐えれるように、「I型アンジオテンシンII受容体(AT1R)」と「β-アレスチン2」という蛋白質が心臓の収縮を強めています。我々は最近、①「β-アレスチンバイアスアゴニスト(BBA)」という薬を用いて、この仕組みを選択的に強めると、ヒト小児心不全のモデルマウスの寿命が延びること、②この薬は、胎児から新生児の心臓の特徴を持つヒトiPS細胞由来心筋細胞でも有効であることを発見しました。本研究会では、この原理を応用した全く新しい小児心不全治療薬を開発することを目指しています。
現在の研究の進捗状況のご報告
2024年9月より、下記の医療機関で行われる開心術において切除され不要となるヒト小児および成人の心筋組織を収集し、β-アレスチンバイアスアゴニスト(BBA)に反応する分子の発現と、その年齢依存性の検討を進めています。
研究参加機関(五十音順):あいち小児保健医療総合センター;大阪医科薬科大学;大阪市立総合医療センター;金沢医科大学;岐阜県総合医療センター;九州大学;京都大学;群馬県立小児医療センター;慶應義塾大学;神戸大学;埼玉県立小児医療センター;静岡県立こども病院;自治医科大学とちぎ子ども医療センター;島根大学;順天堂大学;信州大学;千葉県こども病院;東京慈恵会医科大学;東京都立小児総合医療センター;富山大学;長野県立こども病院;日本医科大学;広島市立広島市民病院;北海道大学(計24機関)


医師および研究者の方へのお願い
- より年長例の人工心肺導入時に切除される心房筋があれば、ご提供ください。
- 完全⼤⾎管転位3型のRastelli術、⼤動脈弁下狭窄の解除術、またはRoss-Konno術などの際に切除される右室流出路以外の部位の検体があれば、ご提供ください。

小児心不全治療薬開発のジレンマとその対策

小児心不全治療薬の開発は、他の小児医療における新薬開発や臨床研究と同様、大変困難な状況です。
具体的には、以下の4つの課題があります。
【課題】
- 市場規模の制約: 小児心不全患者数が成人患者数と比較して少ないため、新薬の開発が経済的に難しいこと。
- 市場へのアクセスの難しさ: 小児用薬の承認取得が遅いこと。
- 倫理的課題: 小児臨床試験における倫理的な配慮と倫理委員会の承認の難しさ。
- これらの理由から、仕方なく成人用に開発された心不全治療薬が適用外使用されていますが、ほとんどの場合その有効性や安全性は科学的に証明されていません。
これらの課題に対して、以下のような対応策が考えられます。
【対応策】
- 小児循環の特性と安全性を踏まえた創薬。
- 政府支援: 小児医療の新薬開発への資金援助や研究助成金の提供。
- 企業の奨励: 制度的なインセンティブを提供して、企業に小児薬の研究開発に取り組むよう奨励。
- 希少疾患連携: 心不全などの希少症例を共有し、国際的な研究とデータ共有を促進。
- 医師教育: 小児科医師の教育と研修を強化して、臨床研究への参加を増やす。
これらの対応策を講ずることで、小児患者の治療オプションを向上させることが期待されます。
本研究会の具体的な活動のご案内

ヒト心筋組織内の蛋白質の発現の解析
(日本小児循環器学会 小児心不全治療薬開発委員会支援研究)
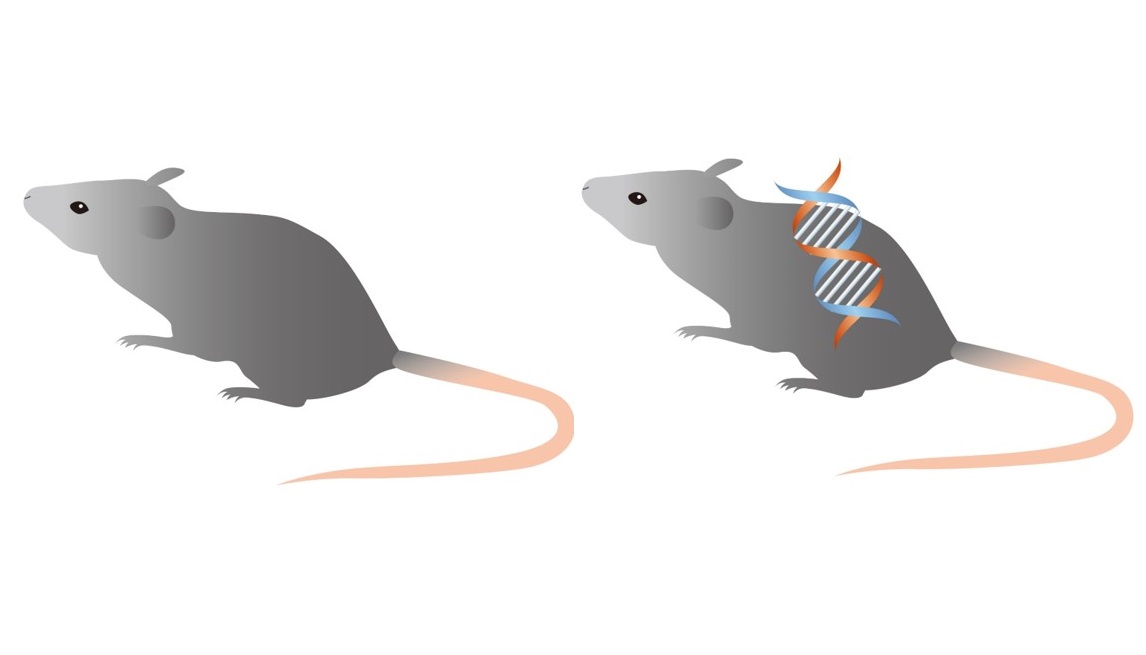
マウスを用いた安全性と有効性の解析
(科研費支援研究)

AT1受容体と小児心不全治療薬の結合様式の解析
(JAXA、BINDS、インタープロテイン社、SpaceBD社支援研究)